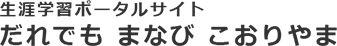本文
清水台地域公民館 まちなか農園
【清水台地域公民館】まちなか農園
郡山のど真ん中、アスファルトばかりの清水台地域でも園芸を楽しめるはず!そんな気持ちから「まちなか農園」はスタートしました。
令和6年度
第4回館外学習会津で学ぶエシカル(9月20日)
西洋ミツバチの巣箱観察でミツバチの生態や自然のつながりを学びました。
安全のためのドレスコードは白い服。参加者の皆さんは白い服に養蜂場で準備してくれた防護ネット付きの白いつば広帽を着け、貴婦人のようです。
第3回プロに教わるまちなか家庭菜園(8月25日)
郡山市のまちなかで家庭菜園?
大根「三太郎」の種をまきました。
生産者とつながる貴重な時間。農業に対する熱い思い、しっかりと受け止めました。
第2回綿から糸へ「体験・糸つむぎ」(7月28日)
昨年収穫した綿がとうとう糸になりました。
糸を紡ぐ歴史は縄文時代にまで遡ります。
糸を紡ぐ歴史を調べていくと、紡績により郡山市が発展したことに気づきます。
縄文遺跡からは石製の紡錘車が発掘されるそうです。現代はシリコン製のスピンドルにかわります。
綿を太すぎず、細すぎず、しかし途中で切れないよう糸にしていくのは繊細な作業です。
第1回は暑い夏をのりきる身体にやさしいハーブティ(6月29日)

ラベンダーがかおる季節。庭の片隅のミントやローズマリーの使い方も気になるというわけで、まちなか農園第1回はハーブ教室です。

カモミール、ミント、バラの香りにつつまれ優雅な気持ちでまちなか農園スタートしました。
令和5年度 主催事業「まちなか農園」
郡山のど真ん中、アスファルトばかりの清水台地域でも園芸を楽しめるはず!そんな気持ちから「まちなか農園」はスタートしました。
最終回 もの作り(生産)から暮らし(消費)まで
まちなか農園で栽培した綿、名付けて「まちなか綿」
最終回は大町の老舗、丸榮ふとん店の片田尚子先生とともに座布団作りです。
材料は収穫した綿と先生が準備してくださった再生綿、なんとカバーは会津木綿。
やさしいまちなか綿と会津木綿の感触に心躍ります。
シート状の再生綿を拡げて、手でちぎり、座布団の形に畳み、カバーに詰めます。
座り心地が悪くなるので、しわやでこぼこができないよう丁寧に綿を畳みます。
会津は綿花栽培の北限といわれます。
郡山でも気温が下がると発芽した綿の成長が止まることが何度もあり、消えてしまうこともありました。
7月にまいた分で収穫できたのはほんの少しですが、自分で育てた綿が形になる感動はひとしおでした。
第5回 袋で育てる郡山ブランド野菜(2)
郡山ブランド野菜 冬甘菜(フユカンナ)はどうなった?
8月5日に植え付けした冬甘菜の品評会の日がやってきました。
大きく育った冬甘菜を持って来るのは大変なので、それぞれがスマホで撮影した画像をプロジェクターに投影しながら鈴木先生が解説します。不慣れなスマホで撮った画像を若手メンバーに手伝ってもらいながら投影します。
「暑くてかわいそうだから、日陰においてたの」
「こんなに虫に食べられちゃって」
「肥料あげたら、みるみるうちに枯れちゃった」
感想もさまざま、失敗もありましたが、猛暑の影響をもろに受けた野菜栽培で得たものは生産者の気持ちを理解することでした。
人権や地域、社会や環境に想いをめぐらせて、よい未来になるように「自分ごと」として行動すること、それがエシカル消費と、まちなか農園1回目で先生が言ってましたね。
「他人ごと」だった野菜栽培が「自分ごと」になりました。
来春の再会を約束して玉ねぎの万吉どんを植え付けしました。
郡山ブランド野菜栽培第2弾は加熱すると抜群のおいしさ玉ねぎ「万吉どん」。
来春にはおいしい玉ねぎを収穫できるはず。
後半は袋栽培とプランター栽培をそれぞれ選択して植え付けです。
今日も野菜と農業への思いを熱く語る鈴木先生。
皆さんが胸に抱えるのは花束ではなく野菜のブーケ。
野菜の栽培は大変でしたが、とにかく楽しかった。
来春、また会おうね。
第4回 春まで楽しむ秋の寄せ植え
「キャベツの調子どう?」
「順調だと思う」
「虫が気になる」
「坊さんの気絶、何回も作ったよ」
同じ趣味をもち、郡山ブランド野菜キャベツの「冬甘菜」(フユカンナ)を育てる仲間ですから、講座前からおしゃべりがはずみます。しかも、今日はビオラやシクラメンの花苗が並ぶ寄せ植え教室。
「皆さんの気分が上がることも寄せ植えには大切なんです」と山田麻弥先生。
普段は殺風景なピロティがジャックオーランタンやパンパスグラスでハロウィンのマルシェ風。

「てるちゃん、どう思いますか?」
いつもは苗字で呼び合いますが今日は普段呼ばれている名前で呼び合うのがルール。
先生の腕にはなんと「やまちゃん」シールが!
まずは鉢選び。テラコッタ、ブリキ、バスケット、樹脂の4種類から選びます。
せっかくだから冒険しちゃおう。
今回人気のバスケットの寄せ植え。
苔がはえたり、朽ちてきたりするバスケットは風化も楽しめる上級者向けでエシカルな素材。
あれれ、手袋にガクト君が!
カラフルなケイトウをブリキの鉢に寄せ植えしました。
ケイトウは冬には終わってしまいますが、その下にはムスカリの球根が眠っています。
第3回 収穫した野菜をおいしく、無駄なく~野菜の保存と調理法~
猛暑が続く今夏。人にも植物にも厳しい夏です。
第1回目では人と社会、環境にも優しいエシカル消費を、第2回目では農家さんと野菜の気持ちを学んだまちなかファーマー。
第3回はエシカルの実践、伊藤麻家先生に大切に育てた野菜をおいしく、無駄なくいただく調理と保存法を教えていただきます。

夏野菜といえばナス。
1品目はナスとトマト、玉ねぎをたっぷり使ったその名も「坊さんの気絶」。
坊さんも気絶するほどおいしいという「パトゥルジャン・イマーム・パユルドゥ」トルコ料理です。
野菜を大量消費できるので、まさにエシカル。アツアツでも冷やしてもおいしい一品。
「自分がおいしければ、料理に失敗はありません。」麻家先生の言葉はいつも前向き。
みんなが勇気づけられました。

2品目は夏野菜のピクルス。色鮮やかな野菜にわくわくが止まりません。
エシカルがテーマのまちなか農園ですから、収穫した野菜はおいしく、そして大切にいただきます。
そのほかにカボチャ豆腐とゴーヤ炒めを作りました。
ごちそうさまでした。
第2回 袋で育てる郡山ブランド野菜 プロに教わる野菜づくり(8月5日)
「清水台で農業講座はできませんか?」の問いに、
郡山で300種類以上の野菜を作る鈴木農場の鈴木光一先生のお答えはあっさりしたものでした。
「できるよ。今はね、袋でできるんだよ。」
「そうだ、ブランド野菜を作ろう。」
なんと、まちなか農園第2回は
清水台地域公民館で、袋で、しかも郡山ブランド野菜の栽培なのです!
郡山ブランド野菜と聞いて思い浮かぶのは「御前人参」ですが、現在14種類あり、
それぞれの味、特徴、そして物語をお聞きしました。
おいしさや見た目だけでなく、栄養価にもこだわるのが郡山ブランド野菜。なんだか誇らしい気持ちになります。
小さな小さな郡山ブランド野菜「冬甘菜」の苗。
なぜか「トウカンナ」と読んでしまう担当者に
慣れているのか「フユカンナ」と、かぶせ気味に、しかし優しく訂正する鈴木先生。
冬甘菜は生で食べても甘く、葉がぎっしりとつまったキャベツで、加熱すると甘みは増し、煮込んだエキスには出汁のようなコクと旨みがあるそうです。
悩める家庭菜園のベテランさん、野菜栽培ビギナー、鈴木農場の野菜ファンとさまざまですが、鈴木先生に野菜づくりのコツを聞きながら植え付けを行いました。
参加者の皆さんは自宅に持ち帰り、玄関やベランダ、家庭菜園の片隅で栽培し、次の11月12日の鈴木先生の回には、品評会をする予定。さあ、猛暑続きですがおいしい郡山ブランド野菜「冬甘菜」を作りましょう。
第1回 地球にやさしい農作業とエシカル消費(7月1日)
園芸教室ですから、さっそく園芸作業をしたいところですが第1回は、なんと2部構成のしっかり座学なのです。
第1部は「エシカル消費って何だろう」。
園芸教室なのに座学、しかも「エシカル消費?」どんなつながりがあるのか気になるところです。
「Sdgs」、「サステナブル」、「フェアトレード」、「持続可能な社会」そして「エシカル」。よく目に、耳にする言葉ですが、実は何をどうしたらいいかわからないというのがみなさんの本音です。消費生活センターの遠藤先生のご講義はとてもわかりやすく様々な気づきがあり、私たちの身の回りの社会問題や消費の裏側で起こっていることに目を向けるきかっけになりました。
第2部は第1部の「エシカル消費」をふまえた上で「綿」、つまり「ワタ」であり「メン」における世界の労働事情や環境問題を知った老舗ふとん店さんならではの取り組みをお話しいただきました。
「まちなか農園」では綿花の栽培から収穫、そして12月には収穫した綿でのもの作りを体験します。収穫量によって受講生のみなさんと何を作るか決める予定です。
綿の中から種を取り出す参加者。「私も栽培してみたい!」
綿花栽培について話す大町の丸榮ふとん店片田先生と自家栽培の綿で作ったハンカチ。