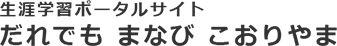本文
令和6年度主催事業報告【粋な男塾】
令和6年度の田村公民館主催事業についてご紹介します。
(プライバシー保護のため、掲載写真には一部ぼかしを入れております)
男性学級「粋な男塾」(令和6年9月~令和7年1月)[全日程終了]
男性学級「粋な男塾」募集チラシ [PDFファイル/416KB]
~講座を通して多種多様な経験を地域活動に生かし、地域貢献・新しい仲間づくり・生きがいづくりの一助としていただきたい~
男を磨き、第2の人生を活き活きと過ごしましょう!塾生の皆さんで事前検討のうえ講座内容を決定し、今年度は全6回の構成となりました。
第1回「開講式_陶芸教室」(令和6年9月7日実施)
自由な発想で一点物の専用皿をつくりましょう。毎年好評で、粋な男塾恒例となりました陶芸教室。今年も金山忍(かなやましのぶ)先生にご指導いただきました。

金山忍先生です。三春町の工房「金山窯」の窯元として、創作活動のほか、陶芸教室など多岐に亘り活動されています。

今年は更に趣向を凝らし、陶器にクォーツ時計を組み合わせます。

時計の型紙を切り抜き、大きさや文字盤の形を参考にしましょう。

その後、5ミリ厚の板2枚に挟むようにして500グラムほどの粘土を置き、成形しつつ、伸ばし棒を前後回転させることで5ミリ厚程度にまで均一に伸ばすことができます。


竹ぐしを使って文字盤の数字やネームなどを自由に彫り込みましょう。クォーツ時計は、焼成後金山先生が後日取り付けをしてくださるそうです。完成が待ち遠しい。


第2回「果実酒造り」(令和6年9月27日実施)
自前の果実酒を自宅で楽しもう。本日はみかんの果実酒づくりを体験します。

日本蒸留酒酒造組合の加賀谷清孝先生に講師としてお越しいただきました。
日本蒸留酒酒造組合<外部リンク>とは(ウィキペディア)

必要材料等は加賀谷先生が準備持参してくださいました。テキストを見て頭に入れながら、さっそく作っていきましょう。

みかんを熱めの湯の中でタワシで洗い、皮をむいて2つに切り、900ミリリットルの広口瓶に250グラム程度入れます。皮もみかん1個分くらいを目安に一緒に入れましょう。

レモンは1個、実だけを輪切りにして入れ、氷砂糖50グラムも入れた後に焼酎甲類を450ミリリットル程度注ぎ入れ、フタをして完成です。

皮は1週間で引き上げ、実は1ヶ月を目安に取り出し、絞ることでより美味しくなるそうです。1ヶ月で飲めるようになりますが、熟成には3ヶ月必要とのことで、味わえるようになるのが待ち遠しいですね。

みかんの果実酒には「風邪予防」「疲労回復」「美白」「美肌効果」「便秘解消」の効果があるそうです。木からもぎたての酸味の強いみかんが良いお酒になるとのことなので、今度は是非、ご自宅での果実酒づくりにチャレンジを!
第3回「館外学習_福島の歴史を学ぶ」(令和6年10月1日実施)※【たむら遊学館】との合同開催
語り部の品竹悦子(しなたけえつこ)先生と巡る、福島の歴史を訪ねる旅。今回は福島方面の神社を訪問しました。




館外研修の行程詳細は、合同開催の【たむら遊学館】ページをご覧ください。
第4回「文化祭支援」(令和6年11月15日~17日実施)
令和6年11月16、17日と開催された【第58回田村地区市民文化祭】の前日準備、そして終了後の会場撤去作業に支援ボランティアとして、男塾塾生の皆さんに尽力いただきました。

【作品展会場(会議室)】実行委員および田村地区行政区の各区長と協力連携しながら、会場設営をしていきます。

作品展示用パネルと脚のはめ込み。重量があるため、安全に配慮しながら複数人での作業です。

【芸能祭会場(大ホール)】設営完了。

田村地区の皆さんで協力し、実施する市民文化祭。多くの来場者に今年度創作活動の成果を鑑賞いただきました。今年はコロナ禍以降中止が続いていた【芸能祭】が5年ぶりに開催ということもあり、例年以上に労力の必要な中、前日準備から文化祭終了後の会場撤去・片付けに至るまで、男塾の皆さんにご協力いただき、円滑に実施ができましたことを感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

第5回「そば・うどんを打つ」(令和6年12月14日実施)
こちらも男塾恒例となった「そば・うどん打ち」
塾生にそば打ちの先生が複数名いらっしゃるため、勝手知ったる仲で和やかに作業は進みます。材料は事前打ち合わせの上、塾生の皆さんで準備調達しました。

【うどん】水と塩の必要分量を量り塩水を準備したら、小麦粉に塩水を加え、手ごねします。そぼろ状に一つにまとまるまでこね、丸く形を整えましょう。できた生地はビニール袋に入れて30分以上ねかせます。

ねかせ終わったら生地を取り出し、軽くこね直し、また20分程度ねかせます。その後打ち粉をし、タテヨコに厚さ3ミリぐらいになるまで伸ばしましょう。伸ばし終わったら再度たっぷりと打ち粉をし、3ミリ幅程度で切ります。

出来立ての【そば・うどん】を塾生で味わう。頑張った甲斐あってコシがあり、美味い!
第6回「焼肉のたれ作り」(令和7年1月18日実施)
前年度に作った【焼肉のたれ】が万能でどんな食材にも合い、味が忘れられない!と塾生の皆さんから強い要望があり、今年も開催!

もちろん今年も講師は佐藤玲子先生、小林エミ子先生のお二方です。どうぞよろしくお願いいたします。


各班別に玉ねぎ、人参、りんご(皮むき)、にんにく、ショウガを切ります。

刻んで、刻んで、刻んで

刻んで、刻んで

刻んで



刻んだ材料をミキサーにかけ砕き、しょうゆを加えながら繰り返し、細かくしていきます。

ミキサーかけが終わったら鍋に入れ、砂糖・酒・みりんを加えて煮立たないようにかき混ぜます。

火を止め、白ごまと一味唐辛子を加えましょう。容器に注いで出来上がりです。1週間から10日ねかせることで熟成されるので、しばしの我慢ですね。タレは常温で1年保存可能で、焼肉だけでなく、豆腐やサラダにかけても美味しく召し上がれます。

ご家族の方もタレの出来上がりを楽しみにしているそうです。来年度も男塾開催の折には、ぜひのご参加お待ちしております!