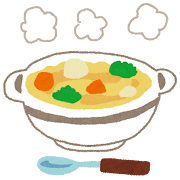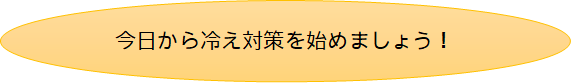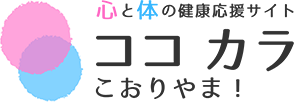本文
【健康コラムVol.15】冬到来!「冷え性」について
みなさんこんにちは!保健所健康づくり課 保健師です。
今回のテーマは「冷え性」です。
現代では、エアコンやファンヒーターなどでいつでも快適な生活ができるようになったため、自力で体温調節をする機会が減りました。このため現代人は暑さ・寒さに弱くなっています。
まもなく本格的な冬到来です。体の冷え対策を万全にして寒い冬を元気に乗り切りましょう!
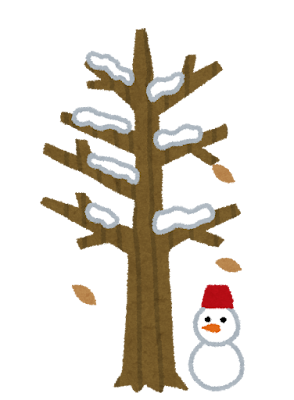
冷え性とは?
人の体には気温の変化に応じて体温を一定に保つ働きがあります。冷え性とは、その体温調節の仕組みがうまく働かず、体が冷え、温まりにくい状態をいいます。
冷え性の原因
冷え性の原因には、筋肉量の減少、基礎代謝の低下、貧血、ホルモンバランスの乱れ、自律神経の乱れ、ストレス、喫煙、薄着や衣類による締め付けなどがあります。

冷え性のタイプと症状
手足が冷える(四肢末端型)
全身の熱量が少なくなると、体の中心に熱を集めようとするため手足が冷えがちです。
手足が冷える他に、肌荒れ・しもやけ・月経トラブル・肩こり・頭痛などの症状を感じやすいことも特徴です。
熱量を増やすためバランスの良い食事を心がけ、適度な運動をしましょう。また、手足に熱を届けるため、おなかや腰を温めるようにしましょう。

内臓が冷える(内蔵型)
ストレスなどが原因で自律神経が乱れると、内臓に血液が行き渡らず、体の内部が冷えることが多いようです。
下痢や倦怠感などの症状が出やすく風邪をひきやすいので要注意です。意識して体を温める食べ物を摂りましょう。(体を温める食べ物については、コラムの巻末をご覧ください。)
下半身が冷える(下半身型)
姿勢の悪さ、骨盤のゆがみ、運動不足が原因で起こりやすく、デスクワークの方に多いようです。こまめなストレッチなど代謝をあげる活動を心がけましょう。(代謝をあげる方法は後述の「いますぐできる対処法」をご覧ください。)

全身が冷える(全身型)
常に体温が低く、冷え性を自覚しにくい方に多いようです。
筋肉量の低下、生活習慣の乱れ、体質が主な原因としてあげられ、倦怠感や下痢、風邪をひきやすいので要注意です。バランスの良い食事と適度な運動をしましょう。

冷え性を放置すると?
冷えが続くと、体は体温を逃さないように血管を収縮させるため、血のめぐりが悪くなります。血液は、酸素や栄養、老廃物を運んでいるほか、全身に熱や免疫細胞も運んでいます。このため血のめぐりが悪くなると、免疫や代謝活動が低下します。
免疫や代謝活動が低下すると、風邪をひきやすい、疲れが取れない、肩こり、腰痛、下痢、便秘、肌荒れ、月経トラブルなどの症状を引き起こします。
いますぐできる対処法
1.運動習慣を身につける
ウォーキングなどの有酸素運動や筋力トレーニングで筋力・体力をつけましょう。

2.体を温める
風呂はシャワーではなく湯船につかりましょう。ぬるま湯(38~40度)に15~20分ゆっくりとつかることがおすすめです。

3.バランスの良い食事
よくかんで食べることや主食・主菜・副菜をそろえてバランス良く食べることが大切です。朝食をしっかり摂り、温かいものを食べましょう。
お菓子、アルコールは控えめに。

4.規則正しい生活をする
生活リズムを整えることは自律神経を整え、冷え性改善に有効です。

5.気候に合わせた衣類を着る
体を締め付けない衣類を着用することも重要です。
また、お腹、3つの首(首・手首・足首)を冷やさないようにしましょう。
6.ストレスをためない
ストレスは体温調節をする自律神経に影響します。

7.ストレッチやマッサージ
血流を促し、自律神経を整えるためにストレッチやマッサージを取り入れましょう。
リラックス効果が期待できます。

体を温めるたべもの
- 未精製の食材(黒糖・胚芽米など)
-
冬が旬/寒い季節にとれる野菜(にんじん、れんこん、ごぼう、ほうれん草など)
-
発酵食品(味噌・納豆など)
-
その他(お肉やお魚などのたんぱく質食材、ビタミンEが豊富なナッツ類やアボカド、ココアなど)