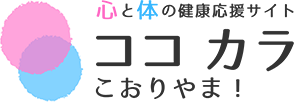本文
#17 健康は食から始まる。食による健康づくりを広める伝道者「食生活サポーター」
食生活サポーター(熱海地区)
専門委員 橋本 和江さん

毎日の食事は、長く健康で生きるための資本になります。食生活は生活習慣そのもの。無自覚のうちに味付けが濃くなっていたり、栄養が偏ってしまっていたりする人も多いかもしれません。今回は、地域で食による健康づくりをサポートする「食生活サポーター」の活動と、その思いをご紹介します。
気軽に相談できるご近所さん
食生活サポーターは郡山市内35地区それぞれに配置されるボランティアで、地域住民へ「正しい食生活の普及」を図り、住民の健康を支える活動を行っています。各地区には、複数人の食生活サポーターとサポーターをまとめるリーダー的役割の専門委員1人がおり、協力して活動しています。食や栄養に関する知識のある人たち……と思う人も多いかもしれません。16年間、熱海地区の専門委員として活動している橋本和江さんに話を聞くと、意外な答えが返ってきました。

「私は栄養士でもないし、食に関する仕事をしたこともありません。ほかのほとんどのメンバーも同じです。
食生活サポーターは、年3回行われる研修会等で健康や栄養に関する最新の情報を学びます。その内容を地域の方と同じ目線で、地域に伝える役割を担っています」
いち生活者として栄養と健康のことを学び、身近な家族や友人に伝達していく。それが、食生活サポーターの役割のようです。では、どんなきっかけで活動を始める人がいるのでしょうか。橋本さんの場合は、義理のご両親の介護だったといいます。
「30年前に、左半身に麻痺のある義父の介護を手伝うために熱海町に引っ越してきました。初めての介護に悩む中、担当のソーシャルワーカーのすすめで、デイサービスで仕事をすることに。そこで、高齢者が飲み込みやすい食べ物や栄養のことなど、食生活への気づきがたくさんあったんです。自宅でよかれと思ってやっていたケアが間違っていたことにも気づきました。
そんな時に、食生活サポーターの先輩から推薦を受けて、活動を始めました。新しい情報をどんどん得られて勉強になりましたし、義父母のおかげで世界が広がりました」
介護の経験を伝える機会にも恵まれているため、気軽に相談できるご近所さんとして頼られているようです。
「減塩を意識して、食事が変わった」
熱海地区では年に数回、地域の方を集めて食生活サポーターが学んだ内容を伝える「伝達講習会」を開いています。2024年11月上旬に熱海公民館安子島分館で開かれた伝達講習会には、近くに住む30人ほどが参加しました。

まずは、推定野菜摂取量を測定する機器で、日頃の野菜摂取量を測定。野菜が不足していたら、味噌汁を具だくさんにしたり、カット野菜を使ったりと、日常的に多く野菜をとるコツを紹介します。

その後、クイズを交えながら「塩分チェックシート」で塩分を取りすぎていないかを確認。塩分の取りすぎは脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まること、出汁や酸味、スパイス、香味野菜を使うとうまみや香りが出て減塩できることを伝えます。

座学を終えたら、本日のメインイベント、調理実習のスタートです。

メニューは3つ。ごまドレッシングのうまみを使った「鶏むね肉とキャベツとミニトマトのソテー」は1人分の食塩相当量が0.9g、減塩柿の種で食感をプラスした「野菜ときのこの柿の種ナムル」は食塩相当量0.4g。「ナメコのみぞれスープ」は食塩相当量1.0g。ごはんと合わせても、食塩相当量はたったの2.3g! 日本人が1日に目標とする食塩摂取量は男性7.5g未満、女性6.5g未満なので、かなりの減塩メニューです。

参加した80代の女性は、数年前から伝達講習会に足を運ぶようになり、食事への意識が変わったと言います。
「しょっぱい食べ物は好きですが、講習を受けに来るようになってからは醤油の代わりにだしの素(塩の入っていないもの)を使ったり、酒やみりんを活用したりと、塩分を減らすことを心がけるようになりました。煮物に塩は入れませんし、ラーメンのスープも飲まなくなりました」

今ではこうした参加者の方も増えてきたと言いますが、橋本さんが活動を始めたばかりの頃は、伝えたいことを受け入れてもらえるのに苦労したといいます。
「地域柄もありますが、やはり皆さんの味付けが濃いのが普段の味。私が食生活サポーターになってはじめて伝達講習をした時は、参加者の方が味見をして『味が薄かったから、砂糖と醤油を足したからね』とおっしゃるんです。みなさん目分量で上手に作れてしまうけど、慣れた味だと塩分が多すぎることがある。意識的に調味料を量って、薄味に慣れていかなきゃいけないと、何度も何度も言い続けました。

私たちも、塩や醤油ではなくともおいしく味付けできる方法を勉強しました。伝達講習会を4回、5回と重ねていくうちに、『ちょっと物足りないけど、この味でいかなきゃなんないんだね』って皆さんわかってきてくださったみたいで。『父ちゃんに出すと醤油をかけられちゃうけど、習った通り減塩が大事だよっていうことを言い続けた』って言ってくれるようになったんです。それだけでも、活動したかいがありました」
より幅広い年代に伝えたい
活動の手ごたえを感じている一方で、より多くの年代に伝えていきたいという思いも膨らんでいるといいます。伝達講習会は平日の昼間に開催していることもあり、参加者の多くは高齢者。食生活サポーターの研修では、子どもの栄養についても学んでいるため知識は豊富ですが、橋本さんはアウトプットの機会づくりに頭を悩ませています。
「夏休みに親子の料理教室を開こうとしても、なかなか興味を持ってもらえなくて、寂しいですね。最近では、市内にある高校のサッカー部の生徒に食育講座を開きました。みんな真面目に素直に聞いてくれるんですよ。これから一人暮らしが始まる子も多いから、自分事として捉えてくれたのかもしれません。これからも、学校や幼稚園などから気軽にお声がけいただき、講座を開ける機会をもっとつくっていきたいです」

みなさんの地域にも、食生活サポーターとして活動をしている人はいるはず。ちょっとしたことでも、食事に関して悩みがある人はぜひ頼ってみてください。
*橋本さんが健康のために意識していることは?
みなさんの健康マイスターになれるように、まずは自分自身が健康でありたいという橋本さん。「医食同源とよくいいますよね。まさに、健康は食からはじまると思っています」と話します。どんなふうに食材を選んでいるのでしょうか。
「地産地消の食材を選び、調味料もなるべく添加物を含まないものを使うようにしています。子どもや孫にも、なるべく自然のものを食べさせてあげたい。すぐ健康に結びつくわけではないけど、コツコツ続けています」

<動画>ショートムービーをご覧ください。
2025年2月26日公開
Photo by 佐久間正人(佐久間正人写真事務所<外部リンク>)
Movie by 杉山毅登(佐久間正人写真事務所<外部リンク>)
Text by 五十嵐秋音(マデニヤル<外部リンク>)