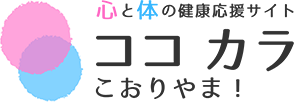本文
#19 30年続く須賀川市「向陽町おてだま会」が、高齢化が進む新興住宅地で育んできたもの
向陽町おてだま会
代表 後藤 幸子さん

同じ時代に、同じ年代が集まってきて家を建てた新興住宅地は、よくあるまちの風景。須賀川市の向陽町には、新興住宅地ならではの課題に向き合い、立ち上げられた地域の女性たちのコミュニティ「向陽町おてだま会」があります。地域のよりどころとして31年。地域の関係性にも変化が生まれてきています。
今回は取材エリアをこおりやま広域圏に拡大し、須賀川市で活動する団体をご紹介します。
支え合って生活できる地域にしたい
向陽町は、郡山市安積町と隣接する閑静な住宅街。スーパーやコンビニもある、郡山市でいう東部ニュータウンのようなエリアです。向陽町おてだま会は、向陽町東集会所で月に2回開催されています。参加者は毎回30人ほど。スタッフ11人が運営を担当し、体操をしたり、民話を聞いたり、ひな祭りやクリスマス会などの季節行事や、コンサートを開くこともあるのだそう。仁井田地区の文化祭に出展する制作物も、力を合わせて作ります。
この場を1995年2月に立ち上げたのは、向陽町に暮らして38年になる後藤幸子さんです。
「おてだま会の目的は、年をとってもこの場所で暮らし続けられるまちづくり、そして高齢者とそれを支える人の生きがいづくりです。地域でともに助け合い、生活を楽しむことで、向陽町で暮らせて良かったと思える地域にしていきたいと考えています」

立ち上げのきっかけは、須賀川市の健康づくり推進員を務めていた後藤さんが覚えた危機感でした。
「新興住宅地なので、ここで暮らすのは地縁のない方ばかり。30年前、この地域で暮らす人はみんな若くて働きに出ていて、近所同士の交流はほとんどありませんでした。でも将来はみんな高齢になる。その時に、互いに支え合いながら生活できるような地域にしたいと思いました」

地域づくりについて考える中、後藤さんは福島県の地域づくりコーディネーター養成講座を受講。地域の調査をしたところ、向陽町には一日中ひとりぼっちで家にいる高齢者が多いことがわかったのです。
「一人でいる時に困ったことがあれば相談できる場をつくりたいと思い、健康づくり推進員の仲間と民生委員、食生活改善推進員の3名に声をかけ、地域の高齢者に『お手玉を作りにきませんか』と呼びかけました。昔あそびって懐かしいけど、なかなか自分だけではやらない。ほわんとしたかんじもあって、参加しやすいかなと思って。だから『おてだま会』って名前にしているんですよ」
参加者16人でスタートしたおてだま会。新型コロナウイルス感染症が流行する以前は一時60人ほどが集まる時期もあったといいます。現在は地元で知らない人はいないコミュニティになり、いわゆる高齢者だけではなく、50代の参加者も足を運んでいます。
地域の老人会の集まりは、年に数回ほど。参加者は回覧板や口コミで伸びていったことからも、こうした場が地域に求められていたことがうかがえます。
「ほかの地域の人にうらやましがられる」
11月のある日に開かれた、おてだま会にお邪魔しました。
午前9時前。60代から90代まで幅広い年代の参加者が集まってきます。迎えるのは、おそろいの緑のエプロンを付けた50~60代のスタッフ10人ほど。参加者にお茶やお菓子を差し出し、話しかけてにぎやかな雰囲気です。

和やかな雰囲気の中でも、スタッフは参加者の顔色にも目を光らせています。行き帰りや会の途中で具合が悪くなる会員もいるため、参加者の体調を確認してからスタートします。
参加者がそろうと、オリジナルソング「おてだま会のうた」をうたいます。元中学校の音楽教師の方に作曲してもらったものだといい、中には歌詞を見ずに歌えてしまう人の姿も。

この日のメインイベントは、須賀川市役所の保健師による体組成や握力測定、体操。みなさんおしゃべりにも忙しそうですが、保健師のアドバイスを聞きながら、自分の身体の状態を確かめていきます。

参加者のひとり、94歳の安田さんは旦那さんが亡くなったことをきっかけにおてだま会に通い始めて25年ほどになるといいます。「みんなでおしゃべりするのが楽しみで。もとは須賀川のまちなかに住んでいましたが、当時の知り合いに会のことを話すと、うらやましがられるんです」とうれしそうに笑います。
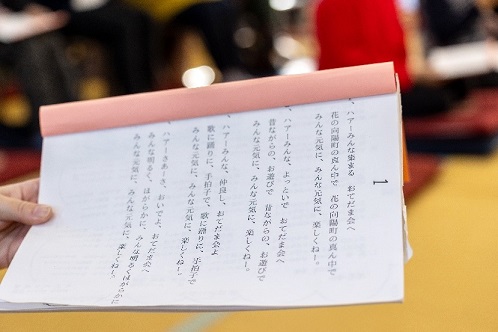
「初めておてだま会を開いたとき、『おはようございます』とあいさつした時と、『またね』『さようなら』と帰られる時とで、表情がぜんぜん違うことに気が付きました。それで、これは意義のあることなのではと確信したんです。いまでも感じますよ。気持ちの変化があるからまた来ようと思ってもらえるのだろうし、私たちも会員さんの変化を感じることで、続けてこられました」

スタッフのやりがいも育む
参加者の中には、誕生日の花束をプレゼントしても、なぜ花をもらったのか理解できないほど認知症が進んでいる方や、足腰が悪く満足に歩くことができなくても来たいという方もいらっしゃるそう。本人が楽しみにしているのなら、家族が通わせたいと思うなら、その気持ちに寄り添いたい。そんな思いから、自力でくるのが難しい人には送迎もしています。

こうした対応は、スタッフが「家族が困った時は私たちが助けになりたい」という思いを一つにしているからこそできること。会が終わると、後藤さんを含むスタッフは毎回2時間ほどその日の反省点や、気づいたことを話し合う時間をとっているのだそう。
「今日の雰囲気いやだな、と思うこともあるんです。でもなぜそう感じるかは、引き出してみないとわからない。気になることがあればなるべく早くキャッチして、解決するのを続けてきた30年でした。トイレなどのサポートを検討しなくてはいけない参加者がいた時にも、共有して次に生かしています。この時間は運営における思いを共有するのにとても大切にしています。
会議では、なるべく一人ひとりの意見をテーブルの上にのせて話し合うことを心がけています。スタッフは自分の意見が採用されたらうれしいでしょうし、やりがいになりますよね。これまでいただいた会員やスタッフからの意見は書き留めています。とにかく楽しくやるのが一番。私にとってはスタッフも、参加者も大きな宝物ですよ」
参加者はもちろん、後藤さんご自身も、スタッフも、楽しめる場であること。それこそが、おてだま会が31年にわたり続いてきた原動力のようです。
引き継げること以上の喜びはない
おてだま会がスタートした1995年に比べ、向陽町でも高齢化が進んでいます。後藤さんも70代になり、引退を視野に入れているのだそう。
「会を通して人と人との関わり、交流が大切ということを伝えてこられたと感じてます。会の運営はスタッフに引き継いでもらって、私は会員として参加し続けることができればこれ以上の喜びはありません」
おてだま会をきっかけに、地域の変化も生まれています。
ある会員の話です。一人で歩いている認知症の傾向がある会員を見かけて声をかけると、向陽町には歩いて行ける場所にパン屋はないのに、パン屋に行くと言うのだそう。心配になり家まで送り届け、事なきを得たのだといいます。
少しずつでも着実に、「支え合える地域」をつくってきたおてだま会。後藤さんたちが培ってきたレールは形を変えながら、これからも地域の心のよりどころとして育っていくことでしょう。
*後藤さんが健康のために意識していることは?
笑顔を絶やさず明るく取材に応じてくれた後藤さん。心身の健康のために、食事や睡眠、運動にも毎日気を使っているそうですが、心の栄養も大切にしているのだそう。
「読書をしたり、絵を描いたり字を書いたり……時間が足りませんが、趣味を大事にしているから、心穏やかでいられるのでしょう。美しいものをいつまでも美しく見られるような心でありたい。そうすると、生きてる喜びが感じられるんです。穏やかじゃない日もたくさんありますけどね(笑)。残りの人生をそうして過ごせたらいいなと思って、心掛けています」

<動画>ショートムービーをご覧ください。
2025年3月19日公開
Photo by 佐久間正人(佐久間正人写真事務所<外部リンク>)
Movie by 杉山毅登(佐久間正人写真事務所<外部リンク>)
Text by 五十嵐秋音(マデニヤル<外部リンク>)