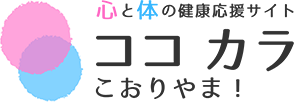本文
こどもの定期予防接種について
予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症から体を守るはたらき)をつくることを言います。赤ちゃんは、お母さんから免疫をもらっていますが、発育とともに自然に失われていきます。また、発育とともに外出や人との接触も多くなり、感染症にかかる可能性も高くなるため、集団生活に入る前に、できるだけ予防接種で免疫をつけましょう!
予防接種の流れ
1 予防接種について理解する
予防接種を受けるときは、郡山市から送付している冊子「予防接種と子どもの健康」もしくは「予防接種説明書」をよく読み、受ける予防接種の必要性・効果・副反応を理解しましょう。
2 医療機関へ予約する
郡山市の予防接種は、福島県内の指定医療機関での個別接種となります。また、医療機関によって受付時間等が異なる場合がありますので、電話で事前に確認してから受診しましょう。
郡山市内の指定医療機関(こどもの予防接種) [PDFファイル/177KB]
※平日午後4時まで接種可能としています。(アナフィラキシーショック等の重大な副反応に備え、平日午後4時以降、土日祝日及び12月29日~1月3日の年末年始は接種不可。)
郡山市内の指定医療機関(日本脳炎予防接種) [PDFファイル/99KB]
郡山市内の指定医療機関(二種混合予防接種) [PDFファイル/109KB]
※中学生以上は、日曜・祝日及び12月29日~1月3日までの年末年始を除く、平日及び土曜日の午後5時まで接種可能としています。
郡山市内の指定医療機関(HPVワクチン) [PDFファイル/116KB]
※HPVワクチン接種は、日曜・祝日及び12月29日~1月3日の年末年始を除く、平日及び土曜日の午後5時まで接種可能としています。
3 予約した医療機関を受診する
接種当日は、お子さんの体調がよいこと、持ち物を準備できていることを確認したうえで受診し、予防接種を受けましょう。
※料金は無料です(対象年齢外は有料となります)。
持ち物
1 母子健康手帳
2 予診票(必要事項を記入して持参してください)
生後1か月頃に郵送される「すくすくセット」に、予診票綴りが同封されています。
日本脳炎(2期)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、子宮頸がん予防ワクチンの予診票は、接種時期に説明書と一緒に郵送します。
予診票を紛失した方、郡山市へ転入した方へ
母子健康手帳を持参し、予診票交付窓口にて交付を受けてください。
| 窓口 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 中央保健センター(郡山市保健所内) | 朝日二丁目15‐1 | 024-983‐8300 |
| 南保健センター(安積行政センター内) | 安積一丁目38 | 024-973-8621 |
| 北保健センター(富久山行政センター内) |
富久山福原字泉崎181‐1 |
024-973-8622 |
| 西保健センター(片平行政センター内) |
片平町字南7‐2 |
024-973-8623 |
| こども家庭課(ニコニコこども館内) |
桑野一丁目2‐3 |
024-924‐3691 |
予防接種記録をなくされた方へ
母子健康手帳を紛失するなどして、予防接種記録をなくされた方は、保健・感染症課(電話:024-924-2163)に御相談ください。
また、予防接種の一番の記録となるのは、母子健康手帳等となりますが、マイナポータルでも予防接種記録の閲覧(※一部の予防接種を除く)が可能です。詳細は、以下を御確認ください。
マイナポータルでの予防接種記録の閲覧方法 [PDFファイル/390KB]
対象年齢及び望ましい時期
望ましい時期に予防接種を受けましょう。
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 |
|---|---|---|---|---|
| ロタウイルス感染症 | ロタウイルスワクチン(1価:ロタリックス) | 出生6週~24週0日後までの間 | 初回 生後2か月~出生14週6日後 (出生15週0日後以降の接種は、安全性が明確ではありません) |
2回 (27日以上の間隔) |
| ロタウイルスワクチン(5価:ロタテック) | 出生6週~32週0日後までの間 | 3回 (27日以上の間隔) |
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 |
|---|---|---|---|---|
|
百日せき ヒブ |
五種混合 | 1期初回 生後2か月~ 7歳6か月に至るまでの間 |
生後2か月~7か月に至るまでに開始 | 3回 (3~8週の間隔) |
| 1期追加 7歳6か月に至るまでの間 |
1期初回接種終了後6か月~18か月後 | 1回 (1期初回(3回)接種終了後1年~1年半の間隔をおく) |
||
| 四種混合の接種歴がある方は、原則四種混合で接種を完了すること。 | ||||
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 百日せき ジフテリア 破傷風 ポリオ |
四種混合 |
1期初回 生後2か月~ 7歳6か月に至るまでの間 |
生後2か月~12か月に至るまで | 3回 (3~8週の間隔) |
|
| 1期追加 7歳6か月に至るまでの間 |
1期初回接種終了後12か月~18か月後 | 1回 (1期初回(3回)接種終了後1年~1年半の間隔をおく) |
|||
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジフテリア 破傷風 |
二種混合 | 2期 11歳~13歳未満 |
11歳 | 1回 | |
予防接種の種類と接種時期と回数
(インフルエンザ菌b型)
5歳に至るまでの間
生後2か月~7か月に至るまでの間
(2回目及び3回目の接種は生後12月未満までに完了)
(27日~56日までの間隔)
初回接種終了後7~13か月の間
(初回接種終了後7~13か月の間隔)
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小児用肺炎球菌 | 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2か月~ 5歳に至るまでの間 |
初回 生後2か月~7か月に至るまでの間 (2回目及び3回目の接種は生後24月未満までに完了) |
3回 (27日以上の間隔) |
|
| 追加 (初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月~生後15月に至るまで) |
1回 (初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降) |
||||
| 接種開始が7か月以降の場合、接種回数が異なります。詳しくは、「小児用肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ」をご覧ください。 [PDFファイル/124KB] | |||||
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
B型肝炎 |
B型肝炎ワクチン | 生後直後~1歳に至るまでの間 |
生後2か月~9か月に至るまで |
3回 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔 3回目:1回目の接種から139日以上の間隔 |
|
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 結核 | BCG | 生後直後~ 1歳に至るまでの間 |
生後5か月~8か月に至るまで |
1回 | |
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻しん 風しん |
麻しん風しん混合ワクチン
|
1期 1歳~2歳に至るまでの間 |
1歳~2歳に至るまでの間 | 1回 | |
| 2期 小学校就学前の1年間 |
小学校就学前の1年間 | 1回 | |||
| (注意)3期(中学1年生相当)、4期(高校3年生相当)の接種は、平成25年3月30日で終了しました。 | |||||
※令和6年度の第1期対象者(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ)及び第2期対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)は、対象期間が令和9年3月31日まで延長されます。詳しくは当ページ下部の「麻しん及び風しんの定期接種の期間延長について」の項目をご確認ください。
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水痘 | 水痘ワクチン | 1歳から3歳に至るまでの間 | 2回 1回目:標準的には生後12月から15月に達するまでの期間 2回目:1回目終了後3月以上、標準的には6月から12月までの間隔 |
||
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本脳炎 | 日本脳炎ワクチン | 1期初回 生後6か月~ 7歳6か月に至るまでの間 |
3歳 | 2回 (1~4週の間隔) |
|
| 1期追加 7歳6か月に至るまでの間 |
4歳 | 1回 1期初回(2回)接種終了後1年おく |
|||
| 2期 9歳~13歳未満 |
9歳 | 1回 | |||
|
平成7年4月2日~平成19年4月1日までの間に生まれた20歳未満の方を対象に、特例措置が設けられています。 [PDFファイル/180KB] |
|||||
| 対象疾病 | ワクチン名 | 対象年齢 | 望ましい時期 | 回数及び間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん | 2価HPVワクチン(サーバリックス) | 小学6年~高校1年相当の女子 | 中学1年の間 | 3回 2回目:1回目の接種から1月 3回目:1回目の接種から6月 |
| 4価HPVワクチン(ガーダシル) | 3回 2回目:1回目の接種から2月 3回目:1回目の接種から6月 |
|||
| 9価HPVワクチン(シルガード9) |
2回または3回 2回接種(1回目を15歳未満で接種)の場合 2回目:1回目の接種から6月 3回接種の場合 2回目:1回目の接種から2月 |
|||
|
令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種していて、接種が未完了である平成9年度から平成20年度生まれの女性は、全3回の接種を公費で完了できるよう経過措置が設けられています。 |
||||
※HPVワクチンについての詳細は、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについてのページをご参照ください。
- 「至るまでの間」「未満」は「誕生日の前日まで」です。
- 予防接種の対象年齢の起算日は、「誕生日の前日から」になります。
麻しん及び風しんの定期接種の期間延長について
令和6年度において、一部のワクチン製造会社の麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の販売停止等により、麻しん風しん混合ワクチンの供給が不安定になりました。
そのため、厚生労働省から接種機会の確保に関する通知があったことを踏まえ、郡山市では、令和6年度中に1期及び2期の対象だった下記の方について、公費での接種が可能な期間を令和8年度末まで延長します。
| 対象者 | 接種可能期間 | |
|---|---|---|
| 1期 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの者 | 令和9年3月31日まで |
| 2期 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの者 | |
| 留意点 |
(例)令和元年7月生まれの児(令和7年度に年長の児)→令和7年4月1日~令和8年3月31日までの1年間が接種期間。
|
|
県外で接種を希望される方へ
郡山市民が県外で定期予防接種を受ける場合、また、市外でおたふくかぜワクチン接種を受ける場合は、郡山市から接種を受ける医療機関へ、予防接種の実施を依頼する書類(依頼書)を作成しています。希望される方は、予防接種前に、郡山市に依頼書交付の申請をしてください。
<注意点>
・依頼書は郵送でお送りします。申請から依頼書が手元に届くまで、10日程かかる場合があります。余裕をもって申請してください。
※依頼書は、保護者や接種を受ける方が、接種を受ける医療機関に持参していただくことになります。郡山市から医療機関に郵送はしていません。
・県外等での接種であっても、郡山市の予診票で接種を受けることになります。紛失等で手元にない場合は、事前に、郡山市の予診票交付窓口で交付を受けてください。
・県外で定期予防接種を受ける場合、市外でおたふくかぜワクチン接種を受ける場合は、一端自己負担でお支払いいただき、保健・感染症課に払い戻しの手続き(※上限金額あり)をしていただく必要があります。予防接種費用の払い戻しのご案内は、依頼書と一緒にお送りしています。
・依頼書の交付を受けずに接種した場合は、郡山市へ費用の請求はできません。また、予防接種が原因で生じた健康被害に関する救済制度が受けられない場合があります。必ず依頼書の交付を受けてから予防接種を受けましょう。
申請方法1 電子申請
以下のURLから申請してください。
※利用者登録が必要となります。
申請方法2 「依頼書交付申請書での申請」
以下の「依頼書交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、保健・感染症課へ申請してください。
定期(A類疾病)予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/93KB]
定期(A類疾病)予防接種依頼書交付申請書 [Wordファイル/45KB]
【提出方法】
・FAX:024-934-2960
・メール:hokenkansen@city.koriyama.lg.jp
・郵送:〒963-8024 郡山市朝日2-15-1 郡山市保健所 保健・感染症課 予防接種担当行
長期療養のため定期予防接種を受けられなかった方へ
予防接種法に基づく定期予防接種は、対象年齢が定められていますが、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、対象年齢のうちに定期予防接種を受けることができなかった方については、定期予防接種の機会が確保されています。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
1.予防接種法施行規則で定める疾病 [PDFファイル/136KB]にかかったことがある方
2.臓器移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
3.医学的所見に基づき、1または2に準ずると認められる方
対象となる定期予防接種
BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、五種混合、麻しん風しん混合、水痘、二種混合、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌、高齢者等帯状疱疹など
対象期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
※ただし、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合と五種混合は15歳未満に限る。
※なお、対象期間・年齢を過ぎて自己負担で受けられた予防接種費用の払い戻しはできません。
接種までの手続き
1.長期療養等理由書 [PDFファイル/105KB]の記載を主治医に依頼してください。
2.理由書下部の「保護者(本人)自署」を記入し、母子健康手帳を持参のうえ、郡山市保健所保健・感染症課へ提出してください。
3.後日、郡山市保健所保健・感染症課より、予診票等の接種に必要な書類が送付されます。書類が届いたら、医療機関で予防接種を受けてください。
定期予防接種に関する健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
詳細は予防接種に関する健康被害救済制度についてをご覧ください。
関連リンク