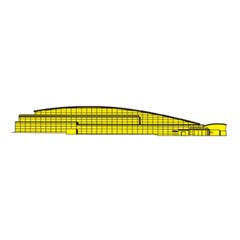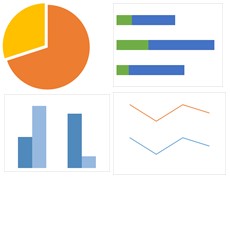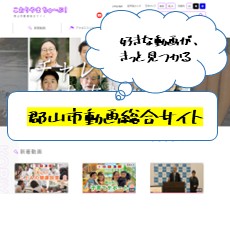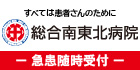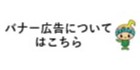本文
『郡山の歴史(2014年10月発行)』 《古代》
6 古墳時代のはじまり
一 大型古墳の出現
弥生時代には、水稲耕作が発展する過程で社会に階級差が生じ、各地に政治的なまとまりが形づくられていった。やがて奈良盆地の東南部を中心とした勢力が、南西諸島と北海道・東北北部を除各地の豪族と連合関係を結び、その証しとして前方後円墳と呼ばれる共通した形の墓を造るようになる。
墓は、土木工事によって造られるので、その大小は、駆り出された労働量に比例する。したがって、その大きさは葬られた人物の政治力と社会における身分を表していることになる。このような人物が葬られた、地上に高く盛り上がった墓を「古墳」といい、これが盛んに造られた時代を「古墳時代」と呼んでいる。
その始まりの時期には諸説あるが、大和の墳墓が巨大な規模となる西暦三世紀(二〇〇年代)の中頃と考える研究者が多い。以後、西暦六〇〇年代まで約四〇〇年間続いた。
古墳時代は、前期(三世紀中頃~四世紀後半)、中期(四世紀後半~五世紀)、後期(六世紀)、終末期(七世紀)に区分されている。
初期の前方後円墳は、奈良県桜井市の箸墓(はしはか)古墳(墳長二七六m)を筆頭に、瀬戸内から九州北部にかけて分布している。これらの古墳は、大和の王が主として鉄素材や鉄製品を入手する目的で開発し連合した、朝鮮半島に至るルート上の豪族達の墳墓と考えられている。前後して、東日本各地の豪族もこの仲間に加わっていった。
二 東北の主な古墳とその立地
古墳は、埋葬される豪族の生前の本拠地に築造された。よって古墳のある場所は、相応の政治勢力の拠点であり、交通の要衝(ようしょう)でもある。
前期の東北で築造された最も大きい古墳は、宮城県名取市の雷神山(らいじんやま)古墳である(墳長一六八m)。次いで、福島県会津坂下町の亀ヶ森(かめがもり)古墳(墳長一二七m)、会津若松市の会津大塚山(あいづおおつかやま)古墳(墳長一一四m)、いわき市玉山(たまやま)古墳墳長(一一三m)と続く。
これらの古墳は、東北南部の主な地域に分布しており、当時の連絡や情報の移動ルートと密接に関連している。亀ヶ森古墳は北陸への、会津大塚山古墳は中通りへの出入り口に当たる場所にあり、玉山古墳付近は、海上交通と関連して成長した政治勢力の本拠だった可能性が高い。このような視点で見ていくと、東北南部の多くの地域を結ぶ位置に立地しているのが雷神山古墳である。この古墳は、東北南部を縦断する阿武隈川と、奥羽山脈に源を発する名取川が太平洋に注ぐ付近に築造されている。阿武隈川の中・上流は福島県中通りのほとんどを占め、宮城県の白石川で分岐すると山形県の置賜(おきたま)へとつながる。また、名取川は、水源を越えると山形盆地に連絡する。一方で、太平洋に面しているのは、海上交通においても重要な場所だったからであろう。
名取に有数の政治勢力が形成され、東北最大の古墳が築造された背景には、東北の中で最も多くの情報が海や河川を介して集まる場所だったことが大きな要因と思われる。
一方、阿武隈川中・上流域に築造された初期の古墳は、須賀川市の仲ノ平(なかのだいら)三号墳(前方後方墳、墳長一七・五m)、大玉村の傾城壇(けいせいだん)古墳(前方後円墳、墳長四一m)、仲ノ平六号墳(前方後方墳、墳長二三・八m)、郡山市正直(しょうじき)三五号墳(前方後方墳、墳長三七m)、大安場(おおやすば)古墳(前方後方墳、墳長約八三m)、須賀川市団子山(だんごやま)古墳(円墳か、直径約五〇m、墳形と規模は流動的)の順に築造されたと考えられる。これらの古墳はいずれも中通り中部に分布しており、北は宮城県角田市や柴田郡村田町まで、南は、栃木県那須まで古墳の空白地帯となっている。前期古墳のこのような分布には、どのような意味があるのだろうか。
各地で古墳が築造され始める前後には、特定の地域で使われていた土器が、地域を越えて大きく移動する現象が見られる。これは、弥生時代の地域の枠を超えた交流が急速に盛んになったからであり、東北南部には、北陸や東海(駿河(するが))で作られた土器が持ち込まれたり、土器の特徴のみが伝わったりしている実例がある。その分布を見ると、北陸の土器は会津を介して中通りに至り、ここで一部南北に分かれるものの、いわきに向って移動しているのに対し、東海(駿河)の土器は、逆に太平洋側を北上し、いわきから阿武隈高地を経て会津まで達している。それぞれの地域の特徴をもった土器が、一方は東へ、もう一方が西へというように方向性をもって移動している事実から、前期の東北南部には、いわきと北陸を結ぶルートが存在し、東西方向に行き来する情報の流れが極めて頻繁だったことがわかる。
以上から、阿武隈川中流域に前期の古墳が集中して築造されたのは、この地域が太平洋と日本海を結ぶ内陸交流の結節点にあたることで、政治勢力の成長が促された結果であったと推定される。
(柳沼賢治)
7 中期の阿武隈川流域
一 中期古墳とその立地
中期になると、前方後方墳はなくなり円墳や前方後円墳など円形原理の古墳だけになる。このことは、地方の豪族達が本格的に大和朝廷の傘下(さんか)に加わった結果と理解されている。
政権中枢の豪族の墓は、この時期に奈良盆地から大阪平野に場所を移し、古墳時代を通して大きさがピークに達する。地方では、それまで築造されていなかった地域に突如として大型古墳が出現したり、またその逆だったりというように、全国的に古墳の築造状況が変化する。これは、大王の権威が著しく強くなり、地方豪族との間に前期とは異なる関係を持つようになったことの現れとされている。
前期に大型古墳がみられた東北では、中期になると一時的に古墳の築造が低調になるが、後半(五世紀後半)には再び活発に転じる。
前方後円墳の北限が岩手県奥州市まで広がり、角塚(つのづか)古墳(前方後円墳、墳長四五m)が築造されたのもこの時期である。前期に大型古墳が数世代にわたって築造された会津盆地では、中期の古墳が極端に少なくなり、大型古墳がみられなかった白河や福島盆地で築造されるなど、地域勢力が浮き沈みするのは全国的な動向と一致している。また、前期のような墳長が一〇〇m前後の古墳はなく、数十mのものが多い。このような現象は、古墳の規模がピークに達する政権中枢と対象的で、大王の権力が強大になったという理解と符合する。
阿武隈川流域では、中小規模の前方後円墳が流域に沿って相次いで築造された(古墳築造の低調な時期もあった)。それらの古墳に立てられた円筒埴輪(えんとうはにわ)には、最も上段の突帯が口縁のすぐ下にあるという共通した特徴が認められる。本宮市の天王壇(てんのうだん)古墳(前方後円墳、墳長四一m)、安達郡大玉村の谷地古墳、伊達郡国見町八幡塚(はちまんづか)古墳(前方後円墳、墳長六六~六八m)、同じく国見町の堰下(せきした)古墳(円墳、直径二一m)、宮城県角田市の間野田(まのた)古墳(円墳、規模不明)、さらに郡山市田村町の大善寺でも採集されており、南北の広い範囲に分布している。遠隔地では、栃木市藤岡町の愛宕塚(あたごづか)古墳などにあり、同じ系統の工人達によって作られたものと考えられている。
中期古墳の分布と埴輪の共通性から、阿武隈川流域の豪族達は政治的に親しい関係をもつと同時に、北関東の豪族を通して埴輪文化を取り入れたものと思われる。
二 朝鮮半島系の文物
五世紀の倭の王は、国内の政治や軍事の権力を握ろうと、中国に使者を送り高い称号を得ようとしていた。また、人的交流や半島からの難民の移住などもあり、先進的な技術や文物が倭国にもたらされた。
古墳時代の人びとは、縄文時代以来の竪穴住居に住んだが、中期になると住居の一画にカマドが造りつけられた。中には、鉄を叩(たた)く台石と炉のある鍛冶(かじ)工房(こうぼう)も見られる。鉄の加工が集落で行われるようになったのである。大槻町清水内遺跡から出土した算盤玉(そろばんだま)形紡錘車(がたぼうすいしゃ)(糸を紡ぐ時に使う弾み車)や田村町南山田一号墳(円墳、一四×一三・八m)から出土した硬質の小型把手付壺(こがたとってつきつぼ)、把手が付き底に複数の孔を開けた蒸し器(多孔式の甑)など、朝鮮半島に由来する文物が急速に普及し、五世紀の列島と半島の交流の影響がこの地に及んだことがわかる。
中期になって加わったねずみ色の須恵器(すえき)は、多くが朝鮮半島から渡来した工人が大阪に開いた官営工房といえる窯場で焼き、北は北海道までの広い範囲に運ばれた。阿武隈川中・上流域、特に南山田遺跡では栃木県宇都宮周辺や宮城県仙台平野と並んで、樽形𤭯(たるがたはそう)や二重𤭯(にじゅうはそう)(小型壺の周囲に透かしが覆う土器)、器台など、特別な時に用いる稀少な器種が目立つ。日常使用するもの以外の稀少な器種を手に入れることのできた集落には、須恵器の流通に関わった集団あるいは有力な豪族が住んでいた可能性が考えられる。
このように、古墳時代中期の阿武隈川流域では、古墳と朝鮮半島由来の文物の分布から、南北方向の交流が格段に高まったとみられる。
(柳沼賢治)
8 後期そして終末の古墳
一 新たな古墳の発見
平成二十二年、田村町にある守山城の発掘調査で直径が約二〇mの古墳(守山城三ノ丸一号墳)が発見された。円の三分の一程しか確認できなかったため正確な形はわからないが、六世紀の後半頃に築造されたこと、埋葬施設が横穴式石室であること、阿武隈川右(東)岸にも埴輪を立てた後期古墳があったこと、出土した埴輪は、北関東や阿武隈川上流域や、いわきの特徴をもっていることなどが明らかになった。
これまでに知られていた郡山盆地の後・終末期古墳には、六世紀後半築造の大槻町にある麦塚(ばくづか)古墳(前方後円墳、全長二六・八m)や七世紀前半に築造された安積町渕の上一号墳(円墳か、直径二〇m)などがある。
麦塚古墳は、埴輪を立てた郡山を代表する後期の有力古墳である。渕の上一号墳は、群馬県高崎市の綿貫観音山(わたぬきかんのんやま)古墳やいわき市の金冠塚(きんかんづか)古墳などに類似する冑(かぶと)などが出土していることで有名である。
これまでは、麦塚古墳や渕の上一号墳の存在から、後期に阿武隈川の左(西)岸に政治勢力が集約され、それが奈良時代の政治拠点である郡衙(ぐんが)(陸奥国安積郡の役所、清水台遺跡)に受け継がれていくと考えられた。しかし、守山城三ノ丸一号墳の発見で、古墳時代後期の郡山盆地には阿武隈川の両岸に二つの政治勢力があったことが明らかになった。
古墳時代の郡山盆地が、その後どのような経緯を経て一つの郡に集約されていったのかという、歴史の推移を理解する上で新たな課題が提起されたと言える。
二 群集墳と横穴墓
古墳には大型のものばかりではなく、小規模で群集するものもある。大型古墳の主を支えた階層の墓であるが、それら小規模な古墳の集まりを「群集墳」と呼んでいる。郡山盆地の大規模な群集墳として、阿武隈川の左(西)岸には大槻古墳群があり、右(東)岸には蒲倉(かばのくら)古墳群がある。大槻古墳群は、かつて一〇〇基ほどあったらしいが、現在ではほとんど残っていない。一基の発掘調査が行われていて七世紀中頃の土器が出土している。
蒲倉古墳群は、直径が約一〇m前後の七一基の円墳からなる(数次にわたる発掘調査によって数が増加している)。この古墳群は、横穴式石室の構造や副葬品(鉄鏃(てつぞく)など)の年代が七世紀と考えられるものの、墓の周囲で行われた祭祀(さいし)で使用した土器は奈良時代のものがほとんどである。これを、時代を超えて利用された古墳群と考えるかどうかは、さらなる検討が必要である。
出土品を観察すると、副葬品には戦闘に使用する鉄鏃が多い。また、同じ時期の集落に比べて須恵器の出土量が多いのも特徴である。その中には製品として流通しないような釉薬(ゆうやく)(焼き物の表面にあるガラス状のもの)が垂(た)れた粗悪品(そあくひん)が含まれ、窯場(かまば)の近くあるいは製作する工人が住んだ集落などで出土するものと似ている。
奈良時代の軍団(古代の軍事組織)に所属する兵士が須恵器の生産にも従事していたことは、窯から出土した瓦に軍団の職名が書いてある例から明らかで、田村町の東山田遺跡でも「火長(かちょう)(軍団の一〇人を統率する役職)」と書かれた文字瓦が出土している。
これらを総合すると、すべての古墳かどうかは別として、少なくとも須恵器の生産や軍事に関わりのある人物の墓が古墳群の中に含まれている可能性が考えられる。今後、石室の構造や副葬品の分析を通して性格を明らかにしなければならない古墳群である。
終末期には、小規模な横穴式石室墳のほかに、崖に横から穴を掘った横穴墓と呼ばれる墓も造られた。田村町小川の蝦夷穴横穴墓(えぞあなよこあなぼ)群(ぐん)は、これまでに二基の発掘調査が行われているが、一二号横穴墓からは柄頭(つかがしら)の形状が円筒状で先が丸い方頭大刀(ほうとうたち)が一振(ひとふり)、一三号横穴墓からも三振の大刀が出土している。一三号墓の一振には、装具の一部に銀象嵌(ぎんぞうがん)されていた。これらの大刀は、中央政府から官人化した地方豪族に与えられた身分を表す品と考えられている。
三 古墳時代から律令時代へ
これまで見てきた後期から終末期の古墳は、現在のところ以下のような順序で築造されたと考えられる。大槻町麦塚古墳→守山城三ノ丸一号墳→安積町渕の上一号墳→蝦夷穴横穴墓群→大槻古墳群→蒲倉古墳群である。
古墳の内容が不明なものがあるものの、後期までに造られた大和政権との連合を示す記念物の前方後円墳はなくなり、古墳の主が影響力を持っていた領域は、七世紀後半以降の律令による中央集権的な行政区画である評(こおり)や郡(こおり)に受け継がれていく。
(柳沼賢治)
9 奈良・平安時代の遺跡と郷
郡山市にある遺跡のうち、奈良・平安時代の遺跡として登録されているのは、約四四〇ヵ所である。古墳時代の遺跡数は約二一〇ヵ所であるから、およそ倍増したことになる。遺跡が立地するのは、阿武隈川をはじめとした河川流域の平地や丘陵地が中心である。遺跡の立地は、古墳時代と奈良・平安時代とで大きな違いは認められない。それは、いずれの時代の社会も、稲作に代表される農業を基盤としていたからだと考えられる。
ただし、古墳時代にはほとんど遺跡の存在しなかった山間地などにも、小規模な遺跡が営まれるようになる。遺跡数の増加は、主にこのような遺跡の出現を反映しており、山間地の開発の進展したことが分かる。七二二(養老(ようろう)六)年、東北地方の耕地開発を奨励する法令が出される。八世紀における遺跡数の増加に、この法令の影響を読み取る見解もある。
遺跡の数は、奈良・平安時代を通じて一定していたわけではなく、時期により増減がある。遺跡数が最も多くなるのは、八世紀末頃から九世紀中頃の平安時代前期である。九世紀後半には減少に転じ、十一世紀中頃の平安時代中期を最後に認められなくなる。ただしそれは、遺跡が消失したのではなく、それまでとは遺跡の立地が大きく変化し、存在しているはずの遺跡が、把握できなくなったに過ぎないと考えられる。この時期に、社会の基盤が大きく変化したことがうかがえる。
遺跡の多くは、竪穴住居(たてあなじゅうきょ)や掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)などから構成される集落である。田村町山中の東山田遺跡(ひがしやまだいせき)、安積町成田の西前坂遺跡(にしまえざかいせき)などは、郡山市を代表する集落遺跡である。集落は大別すると、比較的長く継続する大規模なものと、継続する期間の短い小規模なものがある。このうち大規模な集落は、地域の拠点となる集落と考えるのが一般的で、東山田遺跡や西前坂遺跡はそのような集落である。一方で、継続する期間が短く小規模な集落を拠点的な集落に対する派生的(はせいてき)な集落と捉えたり、拠点的な集落との間で、生業の分業などといった関連を想定する見解がある。
奈良・平安時代には、集落の他にも役所や寺院、生産に関係する遺跡などがある。役所や寺院の遺跡の代表は、清水台遺跡である。詳しくは次項で解説するが、発掘調査によって、古代安積郡の郡家(ぐうげ)の一端が明らかになっている。また、生産に関係する遺跡には、瓦や土器の生産、鉄の生産に関係する遺跡などがある。
奈良・平安時代の行政区画は、国(くに)・郡(ぐん)・郷(ごう)(七一五〔霊亀(れいき)〕元年までは里)からなる。このうち郷は、五〇戸で構成すると決められていた。一戸は二〇〜三〇人からなるから、一郷の人口は一〇〇〇~一五〇〇人程度である。集落に暮らした人々の多くは、戸の一員であったと考えられる。戸によって構成される郷が、集落遺跡と無関係であったとは考え難く、郷の位置を把握するのに、集落遺跡の分布はある程度の手掛かりを提供すると判断できる。
下の図に示したのは、安達郡分置後の安積郡の範囲にある遺跡の分布状況である。一見して明らかなように、遺跡の分布には粗密(そみつ)がある。特に顕著なのは、現在の郡山市中田町や田村郡三春町から田村市・小野町におよぶ、阿武隈山地における遺跡の疎(まば)らさと、遺跡の規模の小ささである。その一方で、阿武隈川沿いの地域や、谷田川の西岸・東岸域、笹原川・逢瀬川・藤田川の流域には比較的多くの遺跡が認められ、規模の大きな遺跡も多い。図中に着色してあるように、中でも谷田川の西岸域と東岸域は、そのような傾向が著しい。安積郡の各郷は、遺跡が濃密に分布し、規模の大きな遺跡が多く存在するこれらの地域を中心に設定されていたと考えられる。
『和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』は、安達郡分置後の安積郡の郷として、入野・佐戸・芳賀・小野・丸子・小川・葦屋・安積の八郷を記載する。各郷の確かな位置は不明ながら、現代の地名との一致によって、芳賀郷は郡山市芳賀、小川郷は郡山市田村町小川(こがわ)、小野郷は田村郡小野町を、それぞれ含む地域であったと考えられる。このうち小野郷は、阿武隈川水系ではない夏井川流域の郷であり、地形的に他郷と区別できる。
小野郷と同じように、奥羽山脈によって地形的に区別できる郡山市湖南町にも、奈良・平安時代の遺跡が存在する。この地域が、奥羽山脈東側の郷に含まれていたのか、単独で郷を構成したのかは判断が難しい。確認されている遺跡数が極端に少ないことと、後の時代の中世に成立する郷である中郷と南郷が、奥羽山脈の東西にまたがって広がることなどは(「相殿八幡神社文書」)、前者の考え方を支持する。一方で、古代の郷は中世の郷に直接的には継続せず、再編されているとする認識もあり、後者の考え方も完全には否定できない。
(垣内和孝)
(参考文献)
垣内和孝『郡と集落の古代地域史』岩田書院 二〇〇八年
郡山市編『郡山市史』第一巻 郡山市 一九七五年
郡山市編『郡山市史』第八巻 郡山市 一九七三年
10 清水台遺跡発掘調査の成果と課題
地域において、最も基本的な行政単位となるのは郡である。奈良・平安時代には、その郡ごとに役所が置かれていた。郡の役所のことを、専門用語では郡家や郡衙(ぐんが)と呼ぶ。どちらが正しいということはないが、本項では、同時代の史料にもみられる郡家の語を用いる。
安積郡の郡家は、現在の郡山市清水台から虎丸町赤木町に広がる清水台遺跡(しみずだいいせき)と考えられている。清水台遺跡では、一九六四(昭和三十九)年から二〇一三(平成二十五)年までの間に、五五地点で発掘調査が行なわれた。一地点の調査面積は小さいのだが、その積み重ねによって、一万三〇〇〇平方メートルを超える面積が発掘された。その結果、大きな成果が得られるとともに、課題も明らかになってきている。
先ず成果として、次の四点が上げられる。瓦や土器といった出土遺物の年代観によって、清水台遺跡の機能していた年代が、七世紀末頃から十世紀中頃であることが判明したこと。(2)掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)や竪穴住居(たてあなじゅうきょ)の向きが、方位から四〇~五〇度斜めに傾くものと、方位とほぼ一致するものとがあり、多くの場合、八世紀前半に前者から後者へ変化していること。(2)「厨」と墨書された土器が集中的に出土する平安時代の遺構群が見つかり、都家の厨家(くりや)と推定できること。(4)瓦が特に集中して出土する範囲が判明したこと。
(1)と(2)は、清水台遺跡の全体像に関わる事柄である。(1)は、一般的に考えられている郡家の継続年代と一致する内容であり、(2)は、評制(こおりせい)から郡制(ぐんせい)への移行を反映する変化と評価されている。すなわち、郡制の施行にともない、建物の向きが方位と一致するものに変えられた可能性がある。
(3)と(4)は、清水台遺跡の個別的な内容に関わる事柄である。郡家は、郡庁(ぐんちょう)・正倉(しょうそう)・館(たち)・厨家(くりや)などから成る。郡庁は、郡の役人が政治や儀式を行なった場所で、広場を囲うように掘立柱建物が配置され、敷地は五〇m四方ぐらいであることが多い。正倉は、住民から税として集めた稲を収めた倉庫で、構造や規模にいくつかのタイプがあり、それらが一定の間隔で並んでいた。館は、国の上級役人である国司(こくし)が国内を巡回する際の宿泊所や、郡の上級役人である郡司(ぐんじ)の宿所として使われた施設。厨家は、国司などの宿泊者や郡の役人に、食事を供給するための施設。清水台遺跡では、これらのうちの厨家の位置が判明したのである。(4)の瓦が集中する場所は、清水台遺跡の中で特殊な位置にあることは確かなのだが、具体的にどのような役割を担った施設が存在したかは判明していない。
次に課題として、次の三点が挙げられる。(5)ある程度の面積を発掘しているにも関わらず、郡庁・正倉・館の位置が判明していないこと。(6)これまでに見つかっている掘立柱建物の規模や構造が、他の地域の郡家とみられる遺跡から見つかった遺構と比較して貧弱であること。(7)瓦の出土量が多く、清水台遺跡には総瓦葺(そうかわらぶき)の建物の存在が想定できるが、都家では板葺きや部分的に瓦を葺く建物が一般的で、総瓦葺の建物は特殊であること。
(5)と(6)は関連する事柄で、郡家を特徴付ける施設である郡庁や正倉が見つかっていないため、掘立柱建物の規模や構造が貧弱であるとも考えられる。しかし(7)は、瓦が集中的に出土している場所が、郡家とは異質な場所であった可能性を示しかねない内容である。総瓦葺の建物として先ず思い浮かぶのは寺院である。瓦が集中的にみつかる場所の近くには、かつて基壇状(きだんじょう)の高まりがあったとの記録もある。基壇とは、堂や塔の基礎となる土台のことで、寺院に見られる構築物である。基壇の上には礎石(そせき)が据えられ、建物はその上に建てられる。開発などによって基壇が削られれば、当然のことながら礎石は動かされ、失われる。また、朱(しゅ)の付着した軒瓦(のきがわら)が出土していることも問題を提起する。朱の付着は柱が朱塗(しゅぬ)りであったことを示すが、朱塗りの柱は寺院では一般的だが、郡家では珍しいからである。
清水台遺跡はかつて、清水台廃寺(はいじ)と呼ばれていた。古代の寺院跡と考えられていたのだが、各地の発掘調査成果を踏まえ、一九七五(昭和五十)年頃から安積郡家と評価されるようになり、遺跡名が清水台遺跡に改められた。
しかし、郡家に近接して寺院が存在するのは一般的な現象である。このような寺院は郡寺(ぐんでら)と呼ばれることが多く、安積郡にも存在したはずである。清水台遺跡についても、郡家か寺院かといった具合に二者択一的に評価するのではなく、両者を総体として把握する必要がある。
また、正倉の位置を考えるに際して興味深いのは、清水台遺跡の南側に当たる高台にかつて存在した「力持(ちからもち)」という字名(あざめい)の辺りで、焼米が掘り出されたとの記録があることである。安積郡の事例ではないが、正倉の火災を伝える記録や、実際に焼米が出土した都家の遺跡も少なくない。安積郡家の実像を解明するには、清水台遺跡の範囲に捉われることなく、周辺にも十分な注意を払う必要がある。
(垣内和孝)
(参考文献)
郡山市教育委員会編『清水台廃寺』郡山市教育委員会 一九六六年
郡山市文化・学び振興公社編『清水台遺跡 総括報告2006』郡山市教育委員会 二〇〇七年
郡山市文化・学び振興公社編『清水台遺跡と古代の郡山』郡山市教育委員会 二〇〇八年
11 安積郡の成立
奈良・平安時代の行政区画は、国・郡・里(七一五〔霊亀(れいき)元〕年に郷と改称、以下では郷と表記)からなる。これらのうち、地域の基本的な単位として重い意味を持ったのが郡である。ただし郡は、時期により名称や範囲に違いがある。奈良・平安時代の郡につながる最初の行政区画は、阿尺国造(あさかこくぞう)の管轄した国である。この国は、大化改新に伴う地方行政制度の改革により、評(こおり)という区画に再編される。阿尺国造の国は、阿尺評になった。その年代は諸説あるものの、六四九(大化(たいか)五)年とする見解が、近年は有力である。阿尺評の範囲は明確にできないが、今日の郡山市・田村市・田村郡・二本松市・本宮市・安達郡の範囲を含んでいたことは間違いない。会津地方に国造の存在が認められないことを重視し、同地方が阿尺評に含まれていたとする見解もある。この説では、『常陸国(ひたちのくに)風土記(ふどき)』にみられる六五三(白雉(はくち)四)年の地方行政区画再編の記事を踏まえ、阿尺評から会津評が分出したと解釈する。その正否については意見が分かれるだろうが、仮にこの見解に従えば、阿尺評はかなり広大な領域を管轄したことになる。
阿尺評の範囲が広大であれば、領域内には複数の有力豪族が存在したはずである。実際に、前時代に築かれた古墳の集中する場所が領域内に複数ある。中通り地方では、現在の郡山市田村町(下図C)、同じく安積町から大町周辺(同B)、本宮市と大玉村の境界付近(同A)という具合に三ヵ所あり、会津地方にも、会津若松市の東部(同F)、喜多方市の南部(同E)、会津坂下町周辺(同D)と三ヵ所ある。これらの地域を本拠とした有力豪族の子孫が評制の時代にも存在したと考えるのが自然である。
評の長官は督、次官は助督と呼ばれたらしい。督や助督は有力豪族から任命されたから、評の領域に多くの有力豪族が存在したとなれば、彼らは競合関係にあったと考えられる。阿尺評から会津評が分出した背景には、地理的な理由とともに、有力豪族層の思惑も働いていた可能性がある。
その後、七〇一(大宝(たいほう)元)年に制定され、翌年施行された大宝(たいほう)律令(りつりょう)によって、行政区画が評から郡に改められ、阿尺評は阿尺郡になる。郡の長官は大領(たいりょう)、次官は少領(しょうりょう)で、督や助督と同じく、郡内の有力豪族から任命された。阿尺郡が安積郡と表記されるようになるのは、七一三(和銅(わどう)六)年に行政地名の改正が命じられてからである。郷は郡の下に設定された行政の単位で、この郷の数の多少によって、郡の等級が定められた。
この時点の安積郡は、今日の郡山市田村市・田村郡・二本松市・本宮市・安達郡の範囲におおむね相当する、と考えるのが一般的である。ところが近年、このような考えに再検討を迫る木簡が、宮城県多賀城市の市川橋遺跡から出土した。問題の木簡には、「安積郡長江郷」と記されていた。長江郷(ながえごう)は、現在の大沼郡南会津町下郷付近に存在したとみられる郷である。平安時代中期の『和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』には、長江郷は会津郡の管轄とされており、木簡の記述とは矛盾する。そこで、『和名類聚抄』の成立以前のある時期までは、長江郷は安積郡に含まれていたとする見解が提示された。その場合、安積郡の範囲は現在の会津地方の南東部にまで広がっていたことになる。ただし、この新見解には否定的な意見もある。
九〇六(延喜(えんぎ)六)年、安達郡が成立する。安達郡の範囲は、現在の二本松市・本宮市・安達郡におおむね相当するから、安積郡の北部の地域を割いて、安達郡は置かれたことになる。残った安積郡の範囲は、現在の郡山市田村市・田村郡におおむね相当する範囲である。
安積郡の範囲は、その後さらに縮小する。その時期は定かでないものの、各地に荘園が成立する流れのなかで、十一~十二世紀頃に、安積郡の阿武隈川東岸の地域が、田村荘として分出したとみられる。この分出は、田村荘としてではなく、田村郡として行なわれ、後に田村郡が田村荘になったとする見解もある。また、田村荘(郡)成立の前後もしくは同時に、小野郷が小野保になる。保(ほう)とは、特定の役所に税を提供するために設定された行政の単位である。このように安積郡は、最終的には現在の郡山市の西部におおむね相当する範囲にまで縮小する。この安積郡の範囲が、中世以降も行政区画として維持され、近代に郡山市が成立するまで継続する。古代末期に成立したこの安積郡の範囲は、行政区画としての安定性が高かったと評価できる。
行政区画分割の問題を考える上で見逃せないのは、分割して成立した領域には、それぞれ古墳が集中して造営された場所が含まれる事実である。そこには有力豪族の存在が想定でき、行政区画の分割と、有力豪族層との関連がうかがえる。
(垣内和孝)
(参考文献)
垣内和孝『郡と集落の古代地域史』岩田書院 二〇〇八年
郡山市編『郡山市史』第一巻 郡山市 一九七五年
郡山市編『郡山市史』第八巻 郡山市 一九七三年
鈴木孝行「市川橋遺跡出土木簡」『考古学ジャーナル』五二五号 二〇〇五年
12 安積郡の古代豪族
郡の上級役人である郡司(ぐんじ)に任命されたのは、かつて古墳に葬(ほうむ)られた豪族の子孫が多かった。中央の政府は、郡内に伝統的な影響力を持つ彼らを郡司に起用することによって、地方の支配を円滑に進めようとしたのである。『続日本紀(しょくにほんぎ)』を始めとする国の正史(せいし)(国史)に、数は少ないながらも安積郡の豪族が登場する。下の表に示したように、一〇事例で九人が記録されている。
七六九(神護景雲(じんごけいうん)三)年の丈部直継足(はせつかべのあたいつぐたり)は、阿倍安積臣(あべのあさかのおみ)の姓を与えられている。彼は、「安積郡人」と呼ばれているように、官職は持っていなかった。しかし、外従七位下(げのじゅしちいのげ)の位階(いかい)は有している。地方在住で位階を有している者は少数であり、彼は郡を代表する豪族であったと考えられる。継足が、直(あたい)というカバネを有していたことも、それを傍証する。カバネは身分を表し、農民層は基本的には持っていなかった。しかも直のカバネは、かつて国造(こくぞう)であった豪族が称していることが多く、継足が阿尺国造(あさかこくぞう)の子孫であったことをうかがわせる。
ただし、位階は「外」の文字が付く外位(げい)である。外位は、主に地方豪族に与えられる位階で、中央の貴族や官人に与えられた「外」字の付かない内位(ないい)とは区別された。中央と地方との格差を示すものと理解してもいいだろう。丈部直継足は、安積郡を代表するような有力豪族ではあったけれども、地方豪族として、中央の貴族や官人からは区別されていたのである。
新しく与えられた阿倍安積臣の姓のうち、臣(おみ)はカバネである。臣は、中央の官人等も称するカバネだが、下位に位置付けられている。姓に阿倍という中央の豪族名が含まれていることは、中央との繋がりが、地方において重い意味を持っていたことをうかがわせる。
七七二(宝亀(ほうき)三)年の丈部継守(はせつかべのつぐもり)は、継足と同じく阿倍安積臣の姓を与えられている。しかし、継足とは異なり直のカバネを称していないことから、別系統の豪族、もしくは同一の系統であったとしても傍系(ぼうけい)の出身であったことがうかがえる。継守は、この時点では位階も官職も有していないが、十九年後の七九一(延暦(えんりゃく)十)年までには、外正八位上(げのしょうはちいのじょう)の位階を授けられ、安積郡の大領(たいりょう)に任じられていた。安積郡の大領とは、安積郡の郡司(ぐんじ)の中の長官のことである。継守が安積郡を代表する有力豪族であったことは疑いない。となれば、安積郡には、継足と継守が属する少なくとも二系統の有力豪族がいて、その勢力も拮抗(きっこう)していたことが推測できる。
このとき継守は、軍糧(ぐんろう)を献上することによって、外従五位下(げのじゅごいのげ)の位階を授かっている。外正八位上から外従五位下へ昇叙(しょうじょ)によって、継守の位階は九階級あがったことになる。軍糧は、東北地方の北部で蝦夷(えみし)と戦っていた中央政府に献上されたものである。中央政府の蝦夷との戦いに、継守は積極的に協力することによって、自らの地位を高めていったのである。
七九七(延暦十六)年の丸子部(まるこべ)古佐美・大田部山前・丸子部佐美・丸子部稲麻呂は、いずれも大伴安積連(おおとものあさかのむらじ)の姓を与えられている。連(むらじ)のカバネは下位に位置付けられ、臣のカバネに次ぐ。賜姓(しせい)以前、四名はカバネを有しておらず、位階を持つ丸子部古佐美も外少初位上(げのしょそいのじょう)とその地位は低い。彼らは、継足や継守に比べれば、勢力の劣る豪族であったと考えられる。この時点で、丸子部佐美は富田郡、丸子部稲麻呂は小田郡に居住している。両郡は陸奥国の北部、現在の宮城県域に存在した郡である。丸子部佐美と丸子部稲麻呂は安積郡の出身で、両郡に移住したのだと考えられる。同じ丸子部の姓を称する古佐美・佐美・稲麻呂の三名は同系統の豪族の可能性が高く、安積郡の郷の一つである丸子郷との関連が考えられる。
八四三(承和(じょうわ)十)年の狛造子(こまのみやつこ)押麻呂は、陸奥安達連(むつあだちのむらじ)の姓を与えられている。狛は高麗に通じ、彼が朝鮮半島に存在した高句麗(こうくり)出身の渡来人(とらいじん)(帰化人(きかじん))の子孫であることがわかる。「安積郡百姓(ひゃくせい)」とあるが、当時の百姓は、江戸時代のように農民に限定される存在ではない。造子は造(みやつこ)と同じで、カバネである。新しい姓に含まれる地名が安達であることから、押麻呂は、後に安達郡として分置される範囲に存在した安達郷に居住していたと考えられる。
八七〇(貞観(じょうがん)十二)年の矢田部(やたべ)今継と丈部清吉は、阿倍陸奥臣(あべのむつのおみ)の姓を与えられている。新しい姓に含まれる地名が、これまでの安積や安達と異なり、陸奥という国名になっている。安積や安達には、それらの地名を含む姓を与えられた人物と、その地域との強い結びつきが感じられるが、陸奥の地名にはそのような土着性はうかがい難い。矢田部今継や丈部清吉の出自(しゅつじ)を考える上で、考慮すべき点であろう。
以上でみたのは、あくまでも国の正史に登場した豪族である。彼ら以外にも、安積郡には大小の豪族が存在したとみられる。このような限られた事例からでも、安積郡に多様な豪族の存在したことが分かる。
(垣内和孝)
(参考文献)
垣内和孝『都と集落の古代地域史』岩田書院 二〇〇八年
郡山市編『郡山市史』第一巻 郡山市 一九七五年
郡山市編『郡山市史』第八巻 郡山市 一九七三年
鈴木啓『福島の歴史と考古』纂集堂 一九九三年
13 安積山と田村麻呂
安積山 影さへ見ゆる 山の井の 浅き心を わが思はなくに
わが国最古の和歌集とされる『万葉集(まんようしゅう)』に、この安積山の歌が収められている。同書によれば、葛城王(かつらぎおう)が陸奥国(むつのくに)に下向した折、国司(こくし)のもてなしが不十分であったために王が不機嫌となったが、前采女(さきのうねめ)が機転を利(き)かせてこの歌を詠(よ)み、その場を和(なご)ませたという。後に『古今和歌集(こきんわかしゅう)』の序文が、難波津(なにわづ)の歌とともに安積山(あさかやま)の歌を取り上げ、「うたのちゝはゝ」と絶賛したため、和歌の中で特別な存在となる。
安積山の歌が詠まれたのは、葛城王が陸奥国へ下向した年である。『万葉集』はその具体的な年次を語らないが、七二四(神亀(じんぎ)元)年に陸奥国府(むつこくふ)の多賀城が完成した際、その「オープニングセレモニー」へ出席のため、葛城王は陸奥国に下向したとの見解がある。歌が詠まれた場所も明記されないが、多賀城と安積郡という二つの考え方がある。また、前采女は歌の作者ではなく、詠者として登場しており、安積山の歌そのものは、これ以前から存在していたとの推定もある。その場合、安積山は都(みやこ)周辺に存在した可能性が高い。大阪府堺市には「浅香山」の地名があり、その候補である。
このように、安積山の歌については不明確な点が少なからずあったが、二〇〇八(平成二十)年五月に公表された滋賀県甲賀市の宮町遺跡出土の木簡(もっかん)は、安積山の歌について多くのことを明らかにした。問題の木簡には、安積山の歌と難波津の歌が、木簡の両面に一首ずつ墨書(ぼくしょ)されており、その年代は七四四~七四五(天平(てんぴょう)十六~十七)年以前と考えられている。十世紀初頭に成立した『古今和歌集』のはるか以前から、二つの歌はセットで認識されていたのである。このような状況は、安積山の歌が、葛城王の陸奥国下向以前から存在していたとする推定とも符合する。都でよく知られていた和歌を鄙(ひな)の陸奥国で聞いたからこそ、都人である葛城王は、機嫌を直したのだと考えられる。
歌が詠まれた場所は、葛城王をもてなしたのが陸奥国司であったとすると、陸奥国府の多賀城と考えるのが自然である。しかし、歌の詠まれたのが七二四年とすると、多少の問題が生じる。この年は、石背国(いわせのくに)(中通り・会津地方)と石城国(いわきのくに)(浜通り地方)が、陸奥国へ併合される年である。葛城王をもてなしたのが、廃止される石背もしくは石城国司であった可能性も否定できないからである。安積郡は石背国の管轄であり、石背国府が安積郡に存在していたとすれば、アサカの音の通じる場所で歌が詠まれたことに、葛城王が興を感じたとも想像できる。
安積山の歌のように、歴史上の著名な事柄が、地名の一致などから、地域の歴史の中に組み込まれることは少なくない。坂上田村(さかのうえのたむら)麻呂(まろ)をめぐる伝説もその一つである。田村麻呂をめぐる伝説は、東北地方を中心に各地に存在する。田村の地名に通じることから田村地方にも分布し、三春城を本拠とした田村氏は、田村麻呂の子孫と称している。ただし、田村氏が坂上氏の子孫を称するのは江戸時代になってからで、戦国時代は平氏を称していた。田村地方に田村麻呂の伝説が広まるのは、御伽草子(おとぎぞうし)の「田村草子」の内容を引き継いだ奥浄瑠璃の「田村三代記」などの影響による。この奥浄瑠璃にはいくつかの系統があるようで、伝播(でんぱ)の過程で内容が複雑になったり、地方色を強めたりしたと考えられている。
田村麻呂の出生地を、田村町徳定とする伝説も、悪玉姫(あくだまひめ)をめぐる物語の一つである。土地の女である悪玉姫が結ばれる相手は、田村麻呂ばかりでなく、その父親である苅田麻呂(かりたまろ)とするものがある。当地でよく聞くのは、苅田麻呂と悪玉姫が結ばれて田村麻呂が生まれるという内容である。実際に田村麻呂が誕生したのは七五八(天平宝字(てんぴょうほうじ)二)年である。その前年に苅田麻呂は、橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)の乱に際して、反乱の首謀者の一人に、反乱の妨げにならないようにと都で拘束されたことが確認できる(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)。この時点で苅田麻呂が都に居り、有力な武人の一人と認識されていたことが知られる。世情不安定な時期に、そのような苅田麻呂が、都から遠く離れた陸奥国において、悪玉姫と結ばれたとは考えられない。苅田麻呂が陸奥国と関係を持つのは、七七〇(宝亀(ほうき)元)年に鎮守将軍(ちんじゅしょうぐん)に任じられたのが最初であるが、彼がこの職にあったのは僅か半年ほどである。
古代においては、中央と地方の格差は現代の我々が考える以上である。安積郡を代表する豪族である阿倍安積臣(あべのあさかのおみ)が、大量の軍糧(ぐんろう)を献上して得たのは、外従五位下(げのじゅごいのげ)という位階(いかい)に過ぎなかった。かりに田村麻呂が陸奥国の出生だとすると、たとえ父親が中央の武人である苅田麻呂だとしても、大きなハンデを背負っていたことになる。生前に正三位大納言(しょうさんみだいなごん)という公卿(くぎょう)にまでなることは、できなかったと考えるのが自然である。
(垣内和孝)
(参考文献)
大塚徳郎『坂上田村麻呂伝説』宝文堂出版 一九八〇年
郡山市編『郡山市史』第一巻 郡山市 一九七五年
郡山市編『郡山市史』第八巻 郡山市 一九七三年
栄原永遠男『万葉歌木簡を追う』和泉書院 二〇一一年
鈴木啓「安采女と多賀城創建」『福大史学』第七四・七五号 二〇〇三年
14 仏と神
現代を生きる私たちと違って、古代に生きた人々は、仏(ほとけ)や神(かみ)といった存在と真摯(しんし)に向き合っていたと思われる。そうであるとすれば、古代の安積郡を考えるに際して、仏や神といった宗教的な事柄を軽視することはできない。とりわけ古代においては、中央の政府が、法律である律令(りつりょう)とともに、当時の東アジアで広く受け入れられていた仏教を積極的に受容し、統治の手段としても利用していた。国ごとに国分寺や国分尼寺が置かれたことに、それは如実(にょじつ)に示されている。郡ごとにも、郡寺(ぐんでら)と通称される寺院の存在していたことが分かってきている。安積郡にも郡寺が存在したとみられるが、その確かな位置は判明していない。
この郡寺とは別に、安積郡に存在した寺院の記録が『日本三代実録(にほんさんだいじつろく)』にある。八八一(元慶(がんぎょう)五)年、安積郡の弘隆寺(こうりゅうじ)が天台別院(てんだいべついん)となったことが記されている。天台宗の重要な寺院を意味する天台別院となった弘隆寺は、天台宗の地方布教の拠点になったと考えられる。弘隆寺の所在について確かなことは不明ながら、現在の二本松市木幡の治陸寺(ちろくじ)を弘隆寺の後身とする伝承がある。かつて木幡山を敷地とした治陸寺は、山林修行を重んじた天台宗寺院の立地としてふさわしいことから、伝承を支持する見解も出されている。
安積郡の郡寺や天台別院となった弘隆寺は、おそらく堂や塔といった伽藍(がらん)を伴う本格的な寺院であったとみられる。そのような場での仏教は、豪族層によって担われ、国家や豪族のための法会(ほうえ)が催されたと考えられる。しかし仏の信仰は、より下層の人々の間にも広まっていた。
仏教説話集(せつわしゅう)の『日本霊異記(にほんりょういき)』には、村の中に存在する仏堂(ぶつどう)が登場し、全国各地の遺跡においても、この仏堂とみられる遺構が見つかっている。富久山町堂坂の妙音寺遺跡(みょうおんじいせき)でも、仏堂の可能性のある掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)が見つかった。この建物は、西・南・東の三面に庇(ひさし)を持ち、柱穴の一つからは数珠玉(じゅずだま)が出土した。確かなことは不明ながら、堂内には金銅製(こんどうせい)の小さな仏像が安置されていた可能性がある。また、田村町山中の東山田遺跡(ひがしやまだいせき)からは、瓦塔(がとう)と呼ばれる焼き物の塔の破片が出土した。瓦塔は、寺院に存在する建築物としての塔を模して造られたものである。東山田遺跡の一画に、仏を信仰する場が存在していたことは疑いない。おそらく古代の村人たちは、村の一画に建てられた仏堂などに詣(もう)で、病気の平癒(へいゆ)や現世での幸福を仏に願ったのであろう。
古代の村には、土地の神を祀った社(やしろ)も存在した。神前では、春には豊作を祈念する祭りが、秋には収穫に感謝する祭りが行なわれた。このような村の社を管理し、祭りを主宰したのは、村の有力者であった。彼らは、春には稲を村人に貸し付け、秋には利息を付けて返還させたりしていた。村の社が、村の有力者と村人とを結び付ける役割をも果たしていた。
安積郡には、このような村の社ばかりでなく、中央の政府や陸奥国(むつのくに)が管理した神社が存在した。そのような神社は式内社(しきないしゃ)と呼ばれ、安積郡に三社あった。宇奈己呂別神社(うなころわけじんじゃ)・飯豊和気神社(いいとよわけじんじゃ)・隠津島(おきつしま)神社(じんじゃ)である。式内社を名乗る神社は、現在も存在する。しかしそれらは、江戸時代になってから式内社を名乗っているようであり、本当に式内社であるかどうかは、検討が必要である。
宇奈己呂別神社とされているのは、三穂田町八幡に鎮座(ちんざ)する同名の神社、飯豊和気神社とされているのは、三穂田町下守屋に鎮座する同名の神社である。隠津島神社と称する神社は三社あり、二本松市木幡・湖南町福良・喜久田町堀之内にそれぞれ鎮座する。二本松市木幡の隠津島神社以外は、いずれも郡山市の西部にあって、分布が大きく偏る。このような傾向は、平安時代末期に安積郡の範囲が確定した後の事実に影響され、安達郡や田村荘(郡)や小野保の範囲を除外して、式内社の位置を考えた結果ではないかと疑われる。
このように、式内社の位置は不明確なのであるが、隠津島神社については、その位置を推定する証拠がある。式内社を列記する『延喜式(えんぎしき)』が、隠津島の訓(よみ)を「カクツシマ」とするのである。現在ではオキツシマと読むのが一般的だが、かつてはカクツシマと読まれていた可能性が高い。喜久田町堀之内は、室町時代には「角津島」と表記されており(「相殿八幡神社文書」)、角津島の読みはカクツシマであろうから、角津島は隠津島の当て字となる。そして既に触れたように、角津島である喜久田町堀之内には隠津島神社が鎮座していた。式内社の隠津島神社は、堀之内の隠津島神社である可能性が高いと判断できる。
(垣内和孝)
(参考文献)
郡山市編『郡山市史』第一巻 郡山市 一九七五年
郡山市編『郡山市史』第二巻 郡山市 一九七二年
郡山市編『郡山市史』第八巻 郡山市 一九七三年
郡山市文化・学び振興公社編『清水台遺跡と古代の郡山』郡山市教育委員会 二〇〇八年
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団編『郡山東部16』郡山市教育委員会 一九九五年