本文
慢性腎臓病(CKD)予防について
慢性腎臓病(CKD)を予防しましょう!
3月13日(木曜日)は『世界腎臓デー』です!!
毎年3月の第2木曜日は、腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取組みである「世界腎臓デー」です。
みなさんは腎臓の働きやご自身の腎臓についてどのくらい知っていますか?
この機会に、ご自身の腎機能とそれを守る方法について、確認してみましょう。
腎臓の働き
- 血液をろ過して、老廃物を尿として排泄する
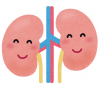
- 血圧をコントロールする
- 赤血球をつくるホルモンを分泌する
- ビタミンDを活性化して骨を強くする
慢性腎臓病(CKD)とは?
腎臓の障害(たんぱく尿など)や腎機能低下(GFR:糸球体ろ過量が60未満)のどちらか、または両方が3か月以上持続する状態をいいます。
実は身近な病気で、日本での患者数は約2,000万人で、成人の約5人に1人が「慢性腎臓病(CKD)」と推計されており、「新たな国民病」ともいわれています。
発病と進行には、生活習慣病が大きく関与しており、予防や進行の抑制には早期発見と早期治療が重要です。
慢性腎臓病(CKD)の原因
慢性腎臓病(CKD)は腎炎などの、もともとの腎臓の病気が原因になる場合もありますが、生活習慣病をともなう場合が増えています。
腎臓には髪の毛ほどの細い血管が多く集まり、ここで血液のろ過をしています。この細い血管に負担がかかると腎臓が疲れてしまい機能が低下します。
つまり、血管に負担をかける生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症)などが、腎臓にダメージを与えるのです。
慢性腎臓病(CKD)の症状
初期には自覚症状はほとんどありません。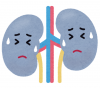
体のむくみや貧血などの自覚症状が現れる頃には、かなり進行している可能性があります。
腎臓は一度悪くなってしまうと、自然にもとに戻ることはほとんどありません。
慢性腎臓病(CKD)の予防のポイント
1.年に一度、健診を受けて、腎臓の働きをチェックする
健診結果では、「尿蛋白」と「eGFR」を確認しましょう
尿蛋白:腎臓に異常があると、尿にたんぱくが排泄されます。【郡山市特定健診では、±(プラスマイナス)以上で受診勧奨です】
eGFR:GFR(糸球体ろ過量)は腎臓の働きをあらわす数値で、数値が低いほど腎臓の働きが悪いということになります。健診では、血清クレアチニン値、年齢、性別から計算するeGFR(推算糸球体ろ過量)を代わりに用います。【郡山市特定健診では、45未満で受診勧奨です】
このほか、健診結果から病院受診をすすめられた方は早めに受診して、治療を始めましょう。
2.正しい生活習慣を送る
肥満の予防
毎日体重を測定し、体重管理をしましょう。
肥満(BMI25以上)がある方は、腹8分目を心がけ、間食を控えるなど、減量に取り組みましょう。
+10(プラステン):今より「10分」活動量を増やしましょう。階段を利用したり、すき間時間に体操やストレッチなど、自分のペースで始めてみましょう。
塩分を控える
塩の取りすぎは、腎臓にダメージを与えます。
塩味以外の「酸味」や「旨味」を取り入れ、「減塩」を心がけましょう。
禁煙する
喫煙は腎臓だけでなく、様々な病気のリスクを高めます。
お酒は控えめに
飲酒は適量を心がけましょう。
お酒に合う料理は、塩分やエネルギー量が多いので、おつまみにも注意が必要です。
3.高血圧・糖尿病などの生活習慣病の治療を適切に受ける
高血圧や糖尿病は腎機能を悪化させます。医療機関を受診し、きちんと治療を受けましょう。
また、自己判断で治療を中断したり、服薬を中止したりするのはやめましょう。
関連リンク
・腎臓を知ろう!慢性腎臓病の予防と治療を心がけましょう(厚生労働省YouTubeチャンネル)<外部リンク>
・CKD(慢性腎臓病)対策について(福島県ホームページ)<外部リンク>
・糖尿病対策について(福島県ホームページ)<外部リンク>
































































